★2016年救歯塾セミナーのプログラムができました
「黒田式コーヌスクローネをマスターしよう」
①近年またコーヌスクローネの良さが見直されてきています
②コーヌスクローネは可撤性義歯としても、歯周補綴としてもメリット多い
③ コーヌスクローネを学べるところが救歯塾以外には見当たりません
④ 少数歯残存症例にはコーヌスクローネが最適で、高齢者にも最適です
第1回:「欠損歯列が読めなければコーヌスクローネはできない」4月24日? 701号
欠損歯列の読み方、なぜコーヌスクローネかを考える
パーシャルデンチャー設計の延長上にコーヌスクローネあり
実習:直感的難易度評価、Eichner分類、咬合支持、 義歯設計デザイン、
第2回:「支台歯形成がコーヌスクローネ成功のスタート」5月22日? 601号
支台歯形成とコノメトリー:マージン形態、平行関係、コーヌス角度
実習: 支台歯形成模型をサベヤーでチェック、6度のテーパーツール
第3回 :「個歯トレーで支台歯の印象採得」6月26日? 606号
支台歯の印象採得を確実に、個歯トレーの作り方・扱い方、接着剤
精度の高い作業模型、ダウエルピンの選び方
実習:個歯トレー製作、支台歯の印象採得
第4回:「技工作業と診療室作業の連携がカギ」7月31日? 601号
治療の進め方のステップ、診療室作業と技工室作業の流れを把握
コーヌスクローネ成功のカギは間接法を理解すること
実習:鋳造、ワックスアップ、間接法の精度に影響する因子などの討論
第5回:「内冠軸面を全周6度がポイント」9月11日? 601号
内冠製作、ミリング技法、レジンコーピング、 製作法のいろいろ
コーヌスクローネ成功の鍵は、支台歯形成と内冠にあり
実習:内冠完成の比較、軸面チェック、6度チェック
第6回:「内冠合着のポイント、義歯製作法のいろいろ」10月16日? 701号
なぜ内冠合着が先なのか、 内冠合着の誤差の考え方
内冠セット後のテンポラリー義歯 、内冠合着後の義歯製作法の流れ、
実習:内冠合着、合着に関する誤差の考え方を討論
第7回:「コーヌスクローネプレゼンと質疑応答討論会」11月13日? 601号
コーヌスクローネに関する「なんでも質問」と「ケースプレゼンテーション」
※懇親会(17:00~19:00)5階 スバル
受講のご案内
★受講のご案内
*口腔内写真を撮っている方を対象。定員70名、先着順で締め切ります。
*受講料:¥100,000円(1年7回連続) 実習があり、連続受講を推奨 実習代の実費負担あり。
*会場:都市センターホテル(千代田区平河町2-4-1 電話03-3265-8211)
*申し込み方法:次の事項を,下記へメールかファックスでお寄せ下さい 氏名,出身校,卒年,受講経験,連絡先の住所〒,Tel,Fax,E-mailを紹介者、何を見て知ったかなど
*亀井歯科 E-mail:kameishika@splash.dti.ne.jp Fax:03-3837-2252 〒110-0016 台東区台東1-31-10-202 電話03-3837-2252
さあ、一緒に学びましょう
救歯塾の特徴であるチュートリアル方式で学ぶことで、着実に実力が向上します。 継続的に受講することがとても大切です。これほど安価で内容のあるセミナーがあるでしょうか?
2015年救歯塾セミナーでのスナップです
開校式に大勢の参加者に感謝しながら、やや緊張気味で「チュートリアル方式のセミナー」を解説します。
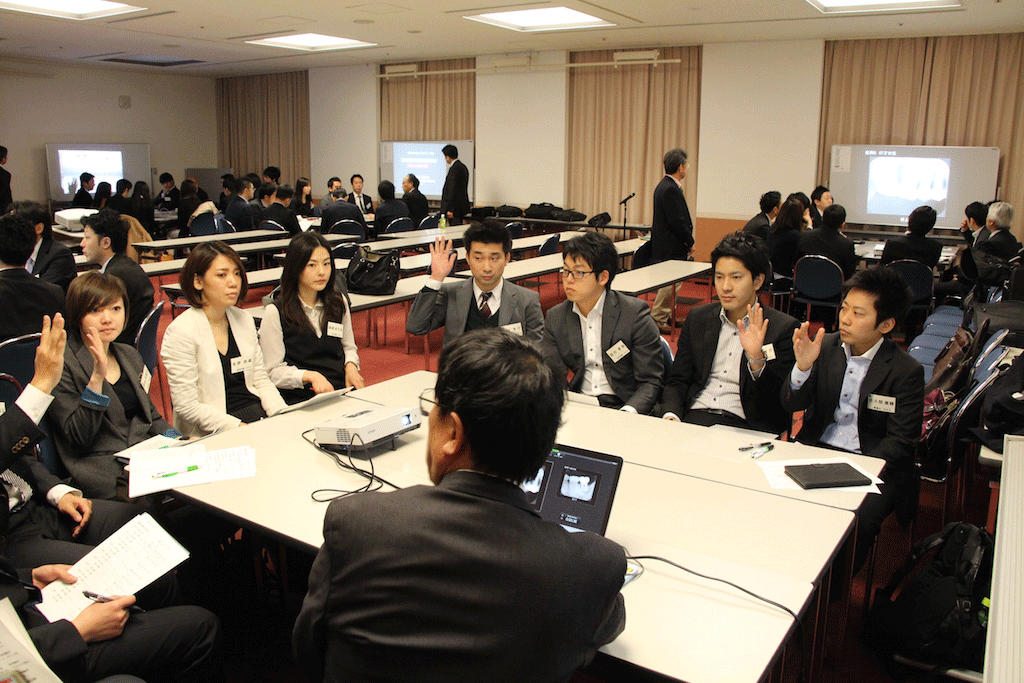 |
|---|
チュートリアル方式は医学系の臨床研修として最も有効な研修です。まず「宿題」が与えられ、レポートを提出します。これによって課題の予習ができます。それを基に「グループ討論」が少人数によって行われます。臨床症例をもとに、診断、処置方針、処置の具体策などを討論します。ただ聞くだけの講演会形式と異なり、発言することでしっかりと頭にたたき込まれます。交代で司会進行と発表者が決められます。各グループにチューターが1名いて、進行の助言などを行います。討論する課題の症例をホワイトボードに映写して、それを全員が見ながら検討していきます。70名の参加者を7つのグループに分けて、各グループが10名以下で討論します。
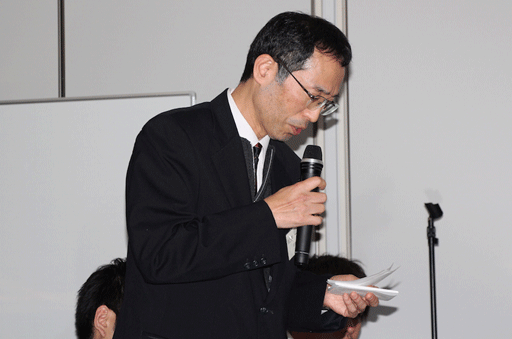 |
|---|
各グループから輪番制で発表者がグループでの結論を発表します。
2015年第1回セミナーが始まりました
今年はすごい参加者数です。70名を超えましたので、満員御礼でお断りさせていただきました。いつもは40~50名くらいの申し込みで、赤字にならないかとやきもきさせられるのですが、3月末の締め切り時点で69名の申し込みですから、「コーヌスクローネ」以来の大盛況です。70名の内訳は、リピーターが30名、救歯会会員が10名(リピーター)、新人が30名です。70名となると、グループ討論が7グループとなって、会場が狭いので1グループがはみ出てしまい、受付でお願いすることになりました。そのために、救歯会の会員には会場外の受付でグループ討論をしていただくことになりました。5月からは実習が始まりますので、会場整理がこれまた大変です。追加の部屋を借りることになります。今年は嬉しい悲鳴を上げております。
今年は参加者のレベルが高くて、受講者が1回目から自らの症例をパソコン持参で持って来てくれました。症例相談や症例討論の時間が足りなくて苦労しています。チューターもハッパを掛けられているような気がします。マンネリにならないように頑張らねばと気を引き締めて始めております。ご期待下さい!
★2015年救歯塾セミナープログラム
「救歯臨床と欠損歯列」
1.歯を抜かれて喜ぶ患者さんはいません
2.危ない歯を救って、長期に保存するには救歯臨床の技術が必要です
3.欠損歯列には う蝕、歯周炎、咬合治療など歯科の多くを含みます
4.欠損歯列はとても難しいですが、教えてくれるところがない
第1回「救歯臨床とは、臨床診断のおもしろさ」4月12日?
救歯臨床とは? 抜歯の基準、口腔内の診かた、問題発見、主訴への対応
患者さんの望む歯科医療とは、抜かずに助ける歯科医療
第2回「救歯臨床の基本は歯内療法と歯周治療」5月17日?
歯内療法、歯周基本治療のポイント(ルート・プレーニング実習)
歯内療法と歯周治療の基本を再考する
第3回「欠損歯列に取り組もうー診断と処置方針」6月14日?
欠損歯列の基本を学ぶ、欠損歯列を読む
診断をする、治療計画を立てる、テンポラリーの大切さ
第4回「欠損歯列にクラスプ義歯かコーヌスクローネか」7月12日?
今までのパーシャルデンチャーの問題点
コーヌスクローネのメリットと問題点を把握しよう
第5回「欠損歯列に自家歯牙移植かインプラントか」9月13日?
自家歯牙移植とインプラントの適応を考える
自家歯牙移植とインプラントのメリットとデメリット
第6回「症例を前にして診断・処置方針立案のプロセス」10月25日?
診断と処置方針、処置方針の立て方を学ぶ
治療のすすめ方をステップを追って検討する
第7回 「全員ケースプレゼンテーション」11月15日?
ケースプレゼンテーションから学ぶ、受講成果
※懇親会:1年間を振り返って(17:00~19:00)スバル
さあ、一緒に学びましょう
救歯塾の特徴であるチュートリアル方式で学ぶことで、着実に実力が向上します。 継続的に受講することがとても大切です。これほど安価で内容のあるセミナーがあるでしょうか?